採用業務の自動化とは?効率化と業務改善を実現する8つの方法を紹介
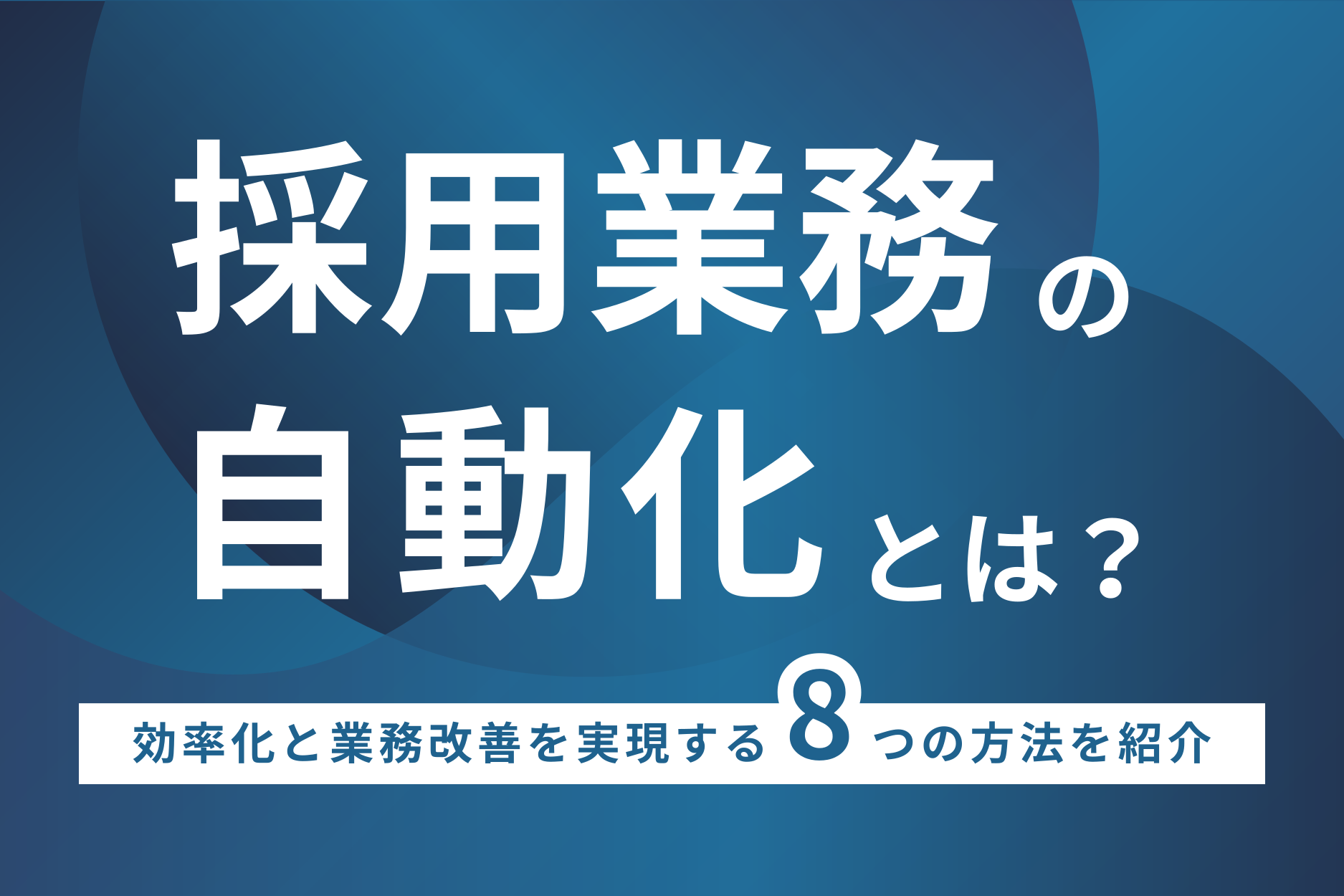
「日々の採用業務が多く、他社に人材がとられてしまっている…」
「採用業務を自動化できる聞くが、何から手を付ければいいのか…」
そんな悩みを抱える採用担当者の方は少なくありません。
応募者対応や日程調整、進捗管理などの事務作業に追われてしまい、本来注力すべき優秀な人材との接点づくりに時間を割けないケースも多いのではないでしょうか。
そこで注目されているのが、採用業務の自動化。
ツールや仕組みを上手に取り入れることで、作業の手間を減らし、採用のスピードや質などを同時に高めることが可能になります。
そこで本記事では、採用の自動化で得られる効果と、すぐに始められる具体策をわかりやすく紹介。
採用業務の自動化とは?
採用業務には、応募受付から選考、内定通知に至るまで、多くのプロセスが発生します。
とくに、日程調整やメール送信など、繰り返し発生する定型業務は、ツールの活用で自動化が可能。
例えば、従来は採用担当者が一件ずつ手作業で行っていた応募者の評価入力や面接日程の調整、合否メールの送信などを、以下ツールを使用して自動化できます。
活用ツール
- ATS(採用管理システム)
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)
- AI面接ツール など
自動化によって、人的ミスの防止や対応スピードの向上が実現し、結果として候補者体験の向上にもつながります。
単に手間を省くだけでなく、採用全体の精度とスピードを高められる点が大きなメリット。
自動化の目的は人員削減ではなく、人が担うべき重要な業務、例えば候補者とのコミュニケーションや採用戦略の立案に集中するためのサポートにあります。
自動化を上手に活用することで、より戦略的で質の高い採用活動が可能になるでしょう。
候補者体験(採用CX)については、こちらの記事もご参照ください。
採用CX(候補者体験)とは?重要な理由から改善の具体例まで解説
採用業務の自動化が必要な理由
採用業務の自動化で、ミスの軽減や効率化するだけでなく、人が担うべき業務に集中できるように。
採用担当者は、人が担うべき業務に集中でき、さらに質の高い採用活動が可能です。
ここでは、自動化に必要な理由の中でも特に重要な4つを解説します。
優秀な人材との接点を増やすため
企業にとって「人財」と言われるほど、優秀な人材の確保が企業成長を左右する重要な経営戦略です。
しかし、実際の現場では、採用担当者が担う業務量は膨大。
求人媒体への掲載や応募者情報の入力、面接日程の調整など、日々の事務作業に多くの時間を割かれています。
その結果、「この人にはぜひ会いたい!」と思う優秀な人材を見つけても、連絡が遅れてしまい、他社に先を越されてしまうケースも少なくありません。
採用競争が激化する中で、スピード感のある対応と、候補者との密なコミュニケーションが必要。
そこで注目されているのが、採用業務の自動化。
事務作業の自動化で、採用担当者は本来注力すべき「候補者とのコミュニケーション」や「採用戦略の立案」に時間を使えるようになります。
結果として、採用活動全体の質が向上し、優秀な人材と出会う機会を増やせるでしょう。
採用担当者の「疲弊」から解放されるため
採用シーズンになると、問い合わせ対応や面接日程の調整が一気に増え、担当者が「朝から晩までメールや電話に追われている…」状況になりがち。
新卒採用のように応募者数が多い場合は、一人ひとりへの対応に多くの時間と労力を要します。
採用担当者の業務例
- 採用計画を立て、求める人材像を明確にする
- インターンや会社説明会を通じて学生や求職者に魅力を発信
- 求人内容を作成し、各媒体に掲載
- 応募者の書類をチェックし、選考を進行
- 候補者との連絡や面接日程の調整
- チーム内での進捗共有や選考会議の実施
- 面接の実施と合否判断
- 内定者へのフォローや入社準備のサポート
こうした「誰がやっても同じ」定型的な作業は、自動化で効率化が可能。
例えば、日程調整ツールの導入で、夜間に届いた応募者からの希望に自動対応でき、漏れを防げます。
採用担当者の負担を減らすことは、採用活動を長く続けていく上で欠かせないポイント。
企業ブランドの向上と採用競争力を強化するため
企業ブランドを高め、優秀な人材から選ばれる力を強化するためには、候補者との円滑なコミュニケーションが欠かせません。
近年、求職者は「応募から面接までのスピード」や「対応のスムーズさ」を企業選びの判断基準にしている傾向。
返信が遅れたり、面接調整に手間がかかると、「この会社で本当に大丈夫かな…」と不安を感じ、他社へ流れてしまうこともあります。
一方で、応募直後に自動返信メールが届き、スムーズに面接日程が決まれば、「対応がしっかりしている」「入社後も安心して働けそう」などの良い印象を与えられます。
自動化によって、企業が「候補者から選ばれる存在」になることが、結果として優秀な人材を確保できる強い採用体制=採用競争力の向上につながります。
採用競争力が高まれば、限られた採用予算でも優秀な人材を逃さず、将来の企業成長を支える人材基盤を築けるでしょう。
採用ブランディングについては、こちらの記事もご参照ください。
採用ブランディングとは?進め方から有効な方法(採用手法)までを徹底解説
採用の責任者として、コア業務に集中するため
採用責任者や人事部長の本来の役割は、「経営戦略に基づいた採用計画の立案」や「組織全体のパフォーマンス向上」などです。
しかし、日々の細かな進捗管理や現場からの問い合わせ対応に追われてしまうと、中長期的な戦略計画の立案に時間を割くことが難しくなります。
どんな人材をどのタイミングで、どの部門に配置すべきかなど、会社全体の成長に関わる重要な問いに答えるためには、十分な思考時間が必要。
自動化によって日々の雑務を減らせば、採用データの分析を通じて、より精度の高い採用戦略を立案できるようになり、感覚ではなく根拠に基づいた意思決定が可能になるでしょう。
責任者は「人にしかできない、付加価値の高い業務」に集中でき、企業全体の成長を力強く後押しできるようになります。
採用業務を自動化・効率化する8つの方法
採用業務を自動化や効率化するためには、ツールの導入や外部サービスの活用が必要。
また、社内の仕組みも整えなければならない場合もあるでしょう。
本項目では、どういったツールや外部サービスの活用が採用活動を大きく前進できるのか解説します。
採用管理システム(ATS)の導入
ATS(Applicant Tracking System:応募者追跡システム)とは、採用活動全体を統合的に管理するシステムのことです。
ATSには以下のような機能が備わっています。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 求人作成・管理 | 募集要項や求人票の作成・編集、掲載状況の管理など、複数媒体の情報を一元化 |
| 募者情報の管理 | 応募者の基本情報や連絡先、履歴書・職務経歴書などのデータをまとめて管理 |
| 選考プロセスの管理 | 選考の進捗状況を一覧で確認でき、面接日程の調整や評価の共有 |
| 内定者のフォロー | 内定通知の送付状況や入社準備の進捗を確認し、必要な連絡やフォローを記録 |
| コミュニケーション機能 | 応募者への一斉メール送信や自動返信、テンプレート機能などで対応漏れを防ぐ |
| 分析・レポート機能 | 応募数や通過率、媒体別の効果などをデータで可視化 |
「採用活動の司令塔」のような存在で、紙やExcelで行っていた採用業務をデジタル化し、効率化の基盤を築くことが可能。
次に、このATSを活用した代表的な業務改善方法をご紹介します。
ATS(採用管理システム)については、こちらの記事もご参照ください。
採用管理システム(ATS)おすすめ14選を比較!無料サービスや選び方を解説
応募者データの一元管理
ATSを導入すると、連携した求人サイトの応募者データを一箇所でまとめて管理できます。
転職サイトや人材紹介などの重複応募の防止。
各チャネルの効果測定や投資対効果などの分析もでき、最適な媒体の使用や採用手法の立案が可能。
また、応募者データを一元管理できることで業務効率が飛躍的に上がります。
例えば、履歴書や職務経歴書、面接の評価シート、メールのやり取りなどのバラバラになりがちな情報を、候補者ごとに紐づけて自動で整理可能です。
これによって、「あの人の履歴書、どこに保存したっけ?」などの混乱がなくなり、人為的ミスの防止ができます。
限られた人数で採用活動をする中では、「いかに効率よく進めるか」が大きな課題。
ATSを導入すれば、「採用に関わるムダなやり取り」や「探す・確認する時間」が減り、本来注力すべき“人を見る時間”を確保できるようになるでしょう。
スカウト・選考状況の自動更新
ATSは、求人媒体から届いた応募者の情報を自動で取り込み、選考の進捗状況を更新してくれます。
たとえば、候補者に面接案内のメールを送ると、自動的にステータスが「書類選考通過」から「一次面接調整中」に切り替わるイメージ。
さらに、面接日程の調整や評価の共有などもできます。
サービス例
- HERP Hire(ハープハイヤー)
チームでの採用を円滑にするATS - ビズリーチ
採用管理機能も充実しているダイレクトリクルーティングサービス
ATSの機能を活用で、「誰が、いつ、どこまで対応したか」が一目でわかるため、重複や人為的ミスが減らせ選考がよりスムーズになります。
また、進捗の見える化によって「どの段階で辞退が多いのか」など課題の分析も可能。
ATSの導入で、複雑な管理業務から解放され、「応募者対応」「面接内容の改善」「採用戦略の見直し」などの業務に集中できるようになるでしょう。
スカウト自動化については、こちらの記事もご参照ください。
スカウトの自動化とは?RPA・AIスカウト・RPOの仕組みと選び方を解説
RPAの活用
RPAは、PC上で行われる定型作業を自動で実行してくれるツールです。
RPAが担う作業は以下のとおりです。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 応募者データの入力・転記 | 求人サイトからATSやスプレッドシートへの情報移行 |
| 書類選考結果の自動送信 | 合否連絡メールの自動配信 |
| 面接日程調整メールの送信 | 候補者や面接官の予定を照らし合わせて自動で提案 |
| 採用進捗の更新・報告書の作成 | 選考ステータスの更新や、日報・週報の自動出力 |
| 入社前の手続きサポート | 必要書類の案内や提出状況の確認 |
RPAの導入で、「求人媒体から届いた応募者情報をまとめる」や「面接結果を関係者へ通知する」などの繰り返し作業を自動化が可能。
結果的に、ヒューマンエラーを減らすだけでなく、求人票の作成や面接によって時間をかけられるようになり、採用業務の質の向上につながるでしょう。
なお、サービス例は下記のとおりです。
サービス例
- UiPath(ユーアイパス)
幅広い業務に対応できるRPAツール - WinActor(ウィンアクター)
NTTグループが開発した国産RPAツール
面接プロセスのオンライン化
オンライン面接ツールの導入で、地理的な制約を受けずに候補者と面接が可能になります。
遠方の応募者や在職中で移動が難しい方でも、好きな場所から参加できるため、優秀な人材と出会うチャンスが広がるでしょう。
さらに、企業側は移動や会場手配の手間を削減でき、スケジュール調整やコスト面の負担を軽減できる点も魅力。
録画機能を活用すれば、当日参加できなかった面接官も後から内容を確認でき、評価のバラつきを防ぎやすくなります。
複数人で情報を共有できるため、判断の精度が高まり、採用後のミスマッチ防止にもつながります。
代表的なツール
- Zoom / Google Meet
社内会議でも使われる汎用的なウェブ会議ツール - SOKUMEN(ソクメン)
採用に特化したオンライン面接ツール
録画・評価共有・日程調整など、必要な機能を搭載
柔軟な面接対応は候補者に好印象を与え、信頼感につながります。
評価基準の統一とフォーマット化
採用面接では、面接官によって「良い候補者」の基準が異なる場合があるでしょう。
ある面接官は「明るい印象」を重視し、別の面接官は「実務経験」を重視するなど、こうした評価のバラつきは、採用の公平性や一貫性を損ねる要因となりかねません。
評価のバラつきをなくすためには、評価項目の明確化とフォーマット化が不可欠。
スキルや経験、人物面(カルチャーフィット)など、評価するポイントを事前に定義し、全員が同じ基準で採点できる仕組みを整えましょう。
例えば、「コミュニケーション能力」の項目も、具体的な評価観点に分解してスコア化できます。評価例は下記のとおりです。
評価例
- 相手の意見を傾聴し、尊重できているか(5点)
- 自分の意見を整理して論理的に伝えられているか(5点)
このように、感覚頼みの判断を減らすことで、採用業務に携わる全員が同じ視点で候補者を評価できるようになります。
スケジュール調整ツールの導入
候補者と複数の面接官の予定を調整する作業は、採用担当者にとって大きな負担。
メールを何往復もやりとりしながら日程をすり合わせるのは、思った以上に時間と労力がかかります。
スケジュール調整ツールの導入で、候補者が空いている時間を選択するだけで自動的に日程が確定。
担当者は「調整メールのやり取りに追われる」状況から解放され、面接準備や候補者とのコミュニケーションなど、より重要な業務に時間を使えるようになります。
さらに、候補者にとっても「すぐに面接日が決まる」「やり取りがスムーズ」などのメリットがあり、企業に対する信頼感や好印象の向上にもつながるでしょう。
結果として、選考スピードが上がり、他社に先を越されるリスクを減らすことが可能。
サービス例
- TimeRex(タイムレックス)
URLを共有するだけで日程調整が完了するツール - 調整さん
シンプルな機能で、大人数の日程調整にも便利
日程調整については、こちらの記事もご参照ください。
面接日程調整ツールおすすめ10選!無料・有料ツールを徹底比較
採用代行(RPO)サービスの活用
自動化や効率化だけでなく、採用代行サービスであるRPO(Recruitment Process Outsourcing)を採用し、採用活動の一部または全体を外部の専門家に委託することもおすすめ。
募集媒体への掲載や応募者スクリーニング、面接日程調整など、幅広い業務を任せられます。
採用代行サービスの活用例は、下記を参考にしてください。
活用例
- 書類選考と日程調整だけを外部に委託する
- スカウト業務を専門のRPO企業に依頼し、ターゲット人材へのアプローチを強化する
採用担当者がコア業務に集中したい企業や、特定職種の採用ノウハウが不足している企業にとってとくに有効。
新卒採用の面接に注力したい場合や、採用市場の動向を踏まえた戦略設計に時間を割きたい場合など、RPOのサポートによって業務を分担できます。
RPO(採用代行)について、こちらの記事で詳しく解説しています。
RPO(採用代行)とは?サービス内容や導入に向いている企業の特徴を解説
RPOについては、こちらの記事もご参照ください。
RPO(採用代行)比較20選!おすすめサービスの費用や特徴を解説します
AI面接の活用
AI面接は、候補者の表情や声のトーン、回答内容などをAIが多角的に分析し、客観的な評価データを提供するツールです。
人間の面接官が陥りがちな「主観的な偏り」や「第一印象による判断ミス」を補正し、一貫性のある採用判断をサポートします。
特に、一次面接をAIに任せることで、担当者はより高度な判断が求められる二次面接、最終面接に集中でき、採用プロセス全体の効率化が可能。
さらに、評価のデータ化によって「どの候補者がどの基準で高評価だったのか」を後から確認でき、透明性の高い採用活動を実現できます。
AI面接の導入で、面接官ごとの評価のばらつきを抑え、採用基準の統一にもつながります。
また、録画データを活用すれば、後から複数の面接官で確認や議論ができ、合否判断の納得度も向上するでしょう。
応募者側も時間や場所を選ばず受験できるため、選考参加率の向上や母集団拡大が期待可能。
AI面接について、こちらの記事で詳しく解説しています。
AI面接とは?サービスの仕組みからメリット・デメリットについて徹底解説
AI面接については、こちらの記事もご参照ください。
AI面接ツールの比較18選!サービスの選び方・大手や企業の導入状況を解説
面接官トレーニングや採用文化の浸透
ここまで自動化を解説しましたが、多くのシステムを導入しても最終的な採用判断をするのは人です。
面接官に対して、評価基準や候補者対応のトレーニングを実践することで、企業全体「一貫した採用文化」が根付きます。
採用文化が整った上で、自動化と人の判断力を組み合わせでより強い採用組織を構築できるでしょう。
例えば、面接官同士で模擬面接を行い、評価観点をすり合わせるワークショップを実施、候補者との対話スキルを高める研修を取り入れることで、面接の質を均一化が可能。
また、採用フロー全体の振り返りを定期的に行い、データに基づいて改善を続けることも効果的。
こうした取り組みは、採用活動の精度を高めるだけでなく、入社後のミスマッチ防止や定着率の向上にもつながり、長期的な組織の成長を支える基盤となります。
自社の採用課題に最適な解決策は?
採用業務を自動化したいと考えても、どのように進めればよいのか迷う方も少なくありません。
大切なことは、企業の課題をみつけ、どの方法が解決に導くか明確にすること。
ここでは、企業が直面する代表的な5つの課題と、最適な解決策を紹介します。
日々の雑務に忙殺されている
採用担当者の中には、「気づけば1日がメール対応や日程調整で終わっている」「本来注力すべき採用戦略に時間を割けない」と悩む方も少なくありません。
こうした状態が続くと、採用活動が停滞するだけでなく、担当者の疲弊やモチベーション低下、ひいては早期離職につながるリスクもあります。
業務過多になる原因の一例は、下記のとおり。
業務過多になる原因例
- 応募者情報をExcelに転記
- 面接官と候補者のスケジュールをメールで何度もやり取りするなど
手作業で行う業務が多いほど時間も労力もかかる上、人為的なミスが発生。
業務過多を軽減するには、自動化を前提とした仕組み作りが欠かせません。
そのため、採用管理システム(ATS)を導入すれば、複数の求人媒体から届く応募情報を一元管理でき、進捗更新も自動化されます。
また、スケジュール調整ツールを活用すれば、候補者が空き時間を選択するだけで面接日程が確定。
メールの往復が不要になり、スピーディーな対応が可能。
さらに、RPAの導入で、応募者データの転記やメール送信などの定型業務も自動化でき、担当者はより戦略的な業務に集中できます。
「人にしかできない仕事」に専念するには、まず仕組みを整え、手作業から解放されることが第一歩。
採用のPDCAが回せず、原因不明の採用失敗が続く
採用活動では、「内定辞退の理由が分からない」「採用した人材がすぐに辞めてしまう」などの課題を抱える企業は少なくないでしょう。
「他社に負けた」「なんとなくよかったから採用した」などの、感覚的な分析にとどまってしまうと、効果的な改善策を打てず、原因が明確になりません。
採用の質を高めるためには、まず評価基準を明確化やフォーマット化が大切。
また、面接官へのトレーニングを定期的に行い、企業としての採用方針や評価軸の共有で、一貫した採用文化を浸透させられます。
さらに、AI面接ツールの導入も有効。
AIが候補者の回答や表情、声のトーンなどを多角的に分析し、客観的な評価データが見られるように。
ただし、自動化の仕組みを取り入れるには一定のリソースが必要です。
自社での対応が難しい場合は、採用代行(RPO)サービスを活用する選択肢もあります。
専門家が採用プロセス全体を支援することで、データを基に的確な成果につながる体制を構築可能。
そもそも採用業務を効率化するノウハウやリソースがない
採用担当者が自分一人しかいない、あるいは採用の専任者がおらず、他の業務と兼任している企業も少なくありません。
結果として、求人を出しても応募対応が遅れたり、候補者とのやり取りが十分にできず、本当に必要な人材を逃してしまうことがあります。
特に、採用の知識やノウハウが社内にない場合や、専門職など採用難易度の高い職種を募集している場合、思うような成果が出にくい傾向。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが、採用代行(RPO)です。
採用活動の一部、または全体を外部の専門家に委託することで、ノウハウ不足やリソース不足を補い、効率的かつ効果的な採用活動を実現できるでしょう。
募集媒体の選定から応募者スクリーニング、日程調整までをプロに任せることで、社内では面接や最終判断である「人にしかできない業務」に集中できます。
さらに、AI面接ツールを活用すれば、応募者が多い場合でも一次スクリーニングを自動化し、限られたリソースでも多くの候補者と接点を持つことが可能です。
外部の力とテクノロジーを組み合わせることで、採用体制が整っていない企業でも、質の高い採用を進められるようになるでしょう。
採用リソースについては、こちらの記事もご参照ください。
採用リソースが不足する原因は?企業への影響や改善ステップを解説
優秀な人材との接点の障壁をなくしたい
地方や海外に住む優秀な人材にアプローチする際、時間やコストが大きな課題となるケースは少なくありません。
また、求人媒体からの応募を待つだけでは、採用したいスキルや経験を持つ人材と出会えないこともあります。
遠方の候補者との面接では、スケジュール調整や来社対応の負担が大きく、結果的に採用機会を逃してしまうことも。
特に、エンジニアやデザイナーなど採用難易度の高い職種では、地域を越えた採用の仕組みづくりが求められます。
このような場合は、面接のオンライン化が重要です。ウェブ会議ツールを活用すれば、候補者はどこからでも面接に参加でき、企業側も移動や会場手配の負担を減らせます。
また、録画機能を使用し、複数の面接官が後から確認可能。
地理的な制約を解消し、より多くの優秀な人材との出会いが期待できます。
さらに、採用代行(RPO)サービスの活用で、自社だけでは接点を持てない候補者にもアプローチが可能。
専門知識とネットワークを持つプロが、特定スキルを持つ人材のスカウトや書類選考などを代行し、採用の精度とスピードを向上します。
採用活動が候補者の満足度を下げている
採用活動は、候補者とのやり取りは企業の第一印象を決める大切な接点。
「この会社は対応が遅いな…」「選考プロセスが不透明で不安だ…」などの印象を持たれてしまうと、内定辞退の増加だけでなく、企業ブランドの信頼低下にもつながります。
実際に、応募者からの返信が遅れたり、面接日程の調整に何日もかかったりすると、候補者の熱量が下がってしまうケースは少なくありません。
丁寧な対応を心がけていても、採用担当者のリソースが限られている場合、一人ひとりに十分な時間を割けないこともあるでしょう。
こうした課題を解決するには、ツールや外部サービスを組み合わせた仕組み化が効果的。
以下のようにツールや外部サービスの活用ができます。
外部サービス活用例
- スケジュール調整ツールを導入
- 採用管理システム(ATS)を活用する
- 採用代行(RPO)サービスの活用
採用管理システム(ATS)の活用で、応募者の情報や進捗を一元管理可能です。
人手が足りない場合は、採用代行(RPO)サービスの活用もおすすめします。
選考連絡や問い合わせ対応などのオペレーション業務を外部に委託することで、候補者への対応スピードと丁寧さを両立できでしょう。
採用業務の自動化で効率化と優秀な人材確保を両立しよう
採用業務の自動化は、単に作業を効率化するための仕組みではありません。
企業が限られたリソースの中で「いかに優秀な人材と出会い、選び、惹きつけるか」競争力を高めるための戦略です。
ATSやRPAなどのツール、AIやRPOなどの専門サービスを活用すれば、担当者は日々の煩雑な作業から解放され、本来注力すべき「人と向き合う採用」に時間を使えるようになります。
候補者との丁寧なコミュニケーションや採用戦略の立案、データをもとにした改善、人にしかできない業務こそ、企業の採用力を左右するポイント。
すべてを一度に変える必要はありません。
まずは自社の課題を見極め、小さな自動化から取り入れてみましょう。
一歩ずつ仕組みを整えることで、採用活動は確実に強く、魅力的なものへと進化していきます。




