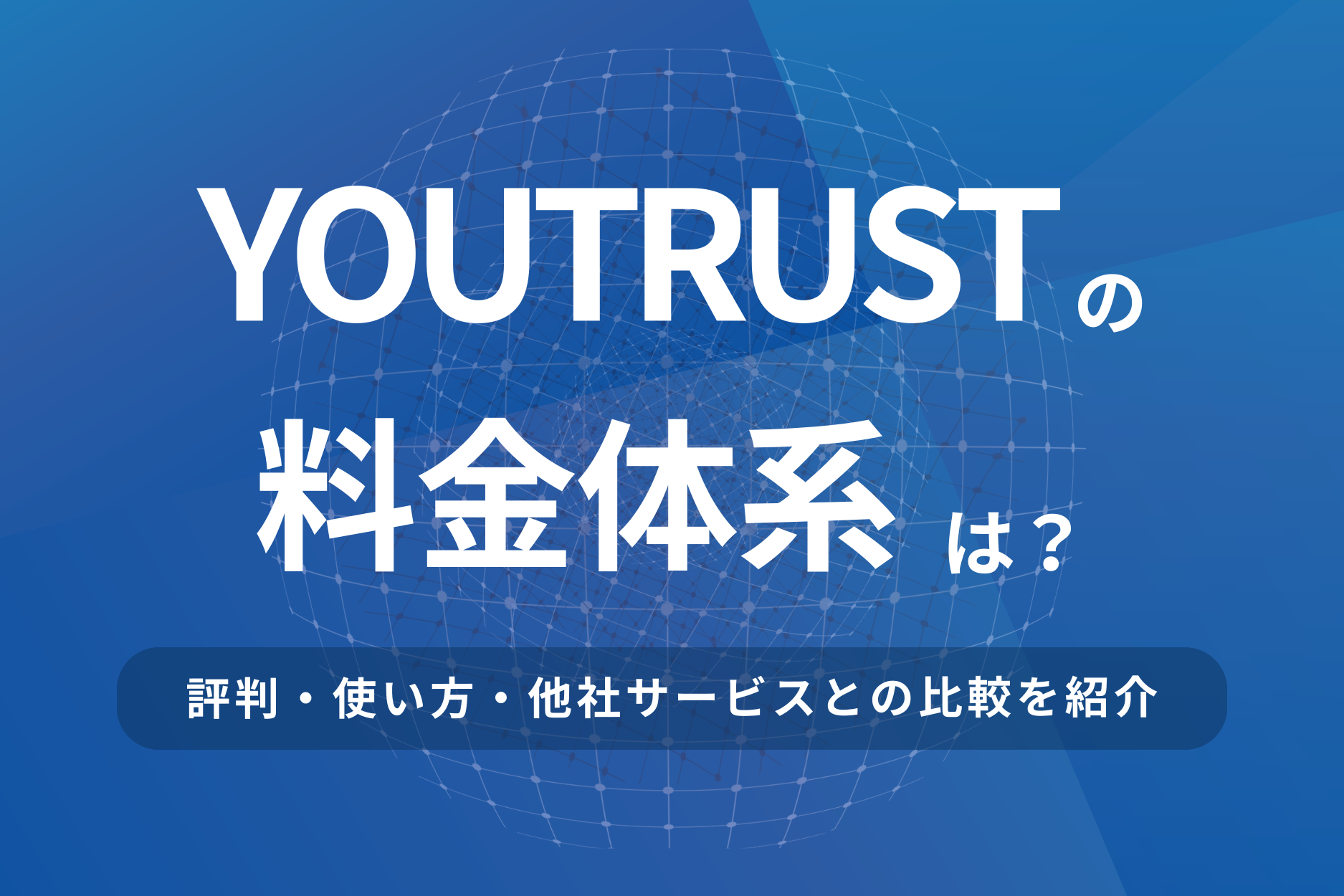SNS採用とは?明日から実践できる採用戦略や成功のコツを徹底解説

SNS採用は、採用コストを抑え、自社に合う人材に直接アプローチできる方法として広がっています。
近年では新卒採用や中小企業での導入も進み、企業文化を伝えやすい手法として注目。
ただ、炎上リスクや運用に手間がかかるなど注意点も存在します。
そこで本記事では、SNS採用のメリットとデメリットを整理し、「LinkedIn」や「Instagram」、「TikTok」などの特徴や活用例を紹介。
さらに、採用コンセプトの設計やコンテンツ戦略、KPI設定といった実践のコツもまとめています。
SNSを活用した採用活動を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
SNS採用とは?
企業の採用活動において、SNSを活用する取り組みが広がっています。
いわゆる「SNS採用」とは、InstagramやLinkedIn、TikTokなどのソーシャルネットワークを通じて求職者へアプローチする手法のことです。
従来の求人広告や人材紹介と異なり、企業側からの情報発信だけでなく、双方向のコミュニケーションを取りながら候補者とつながれる点が特徴。
また、写真や動画を使って社内の雰囲気や働く人の声を伝えられるため、企業文化をリアルに感じてもらいやすいメリットもあります。
その一方で、運用に手間がかかる、炎上リスクがあるなど注意すべき課題も存在。
ここからは、SNS採用の基本を整理しながら、従来の採用手法との違いや注目されている理由を順に見ていきましょう。
従来の採用手法との違い
SNS採用は、これまでの採用手法とは違い、潜在的な人材ともつながれるのが大きな特徴。
従来の求人広告や人材紹介は、転職検討者など顕在層に向けた一方向のアプローチが中心でした。
それに比べ、SNSを活用すれば、Instagramで社内の雰囲気を伝えたり、LinkedInで業界の情報を発信したりと、双方向のやり取りができます。
写真や動画を通じて企業文化を自然に届けられ、候補者に親近感を持ってもらいやすい点も魅力。
採用広報やブランディングと重なる部分はあるもの、SNS採用は応募につながる接点づくりに直結。
従来の枠を超えた「母集団形成」を目指すなら、有効な手法といえるでしょう。
採用ブランディングについては、こちらの記事もご参照ください。
採用ブランディングとは?進め方から有効な方法(採用手法)までを徹底解説
母集団形成については、こちらの記事もご参照ください。
母集団形成とは?やり方・施策・採用成功へのポイントを徹底解説
SNS採用が注目されている理由
SNS採用が注目されている理由は、次のような背景があります。
注目されている理由
- 若年層(15~34歳)の利用率の高さ
総務省の調査でも、20代の多くが日常的にSNSを利用しており、利用時間も長い傾向があります。(参考:令和6年通信利用動向調査の結果|総務省) - 転職サイト利用前の情報収集
求職者の中には、転職サイトや求人媒体で応募をする前に、InstagramやXで企業の情報を調べる人が増えています。 - 企業文化を伝えやすい
写真や動画を活用することで、文字だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や企業文化などの情報を直感的に発信できます。 - アルゴリズムによる表示の最適化
ユーザーの属性や興味関心に基づいてコンテンツが表示されやすくなるため、応募意欲の高い潜在層にも効率的にアプローチができます。 - 早期の接点形成
採用広報の一環として取り入れることで、応募につながるきっかけを早い段階でつくれます。
このように、SNSは候補者と自然につながれる場として、多くの企業から注目されています。
SNS採用のメリット
SNS採用には、従来の採用手法では得られない強みがあります。
ここでは、SNS採用を取り入れることで得られる主なメリットを整理。
潜在層にアプローチできる
SNS採用の大きな利点は、転職や就職をまだ考えていない潜在層にアプローチできる点です。
求人サイトや企業サイト(採用ページ)に訪れるのは、自ら仕事を探している顕在層が中心。
それに対して、InstagramやTikTokのように日常的に使われているSNSでは、情報を探していないユーザーにも自然に企業の魅力を届けることが可能。
その結果、将来的に転職や就職を検討する際に応募へつながる可能性が高まります。
また、接点を持った人材をタレントプール(※1)として蓄積すれば、長期的な採用戦略にも活かせます。
短期の募集効果だけでなく、中長期の人材確保に役立つのがSNS採用の特徴。
(※1):タレントプールとは、企業が将来的な採用候補者を一元管理するデータベースのことです。
企業文化や雰囲気を伝えやすい
SNS採用の大きな魅力は、職場の雰囲気や企業文化を自然に伝えられることです。
企業のWebサイトでは、どうしても堅い印象になりやすいですが、SNSなら動画やストーリーズを通じて日常の様子を身近に・親しみやすい発信が可能。
例えば、社員インタビュー、社員が働く姿、オフィスの雰囲気、社内イベントの様子を投稿すれば、働く姿をイメージしやすくなります。
応募者が社風や働き方を理解できれば、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待。
とくに近年は、待遇だけでなく職場環境や価値観を重視する求職者が増えています。
そのため、SNSを活用して自社の魅力を発信することは、応募意欲を高めるうえで有効な手段です。
採用コストを抑えられる
SNS採用の利点のひとつは、採用コストを抑えられる点です。
求人広告や人材紹介を利用すると掲載料や紹介料が必要になりますが、SNSの活用であれば自社運用だけで情報の発信ができます。
InstagramやXの投稿は無料で始められるため、初期費用をかけずに取り組める点が大きなメリット。
さらに、SNSで有料広告(Meta広告、TikTok広告など)を使う場合でも、ターゲットを絞った配信ができるため、比較的低コストで効果を得られます。
紹介料が発生するサービスと比べても費用を抑えやすく、限られた予算の中で成果を出したい企業にとって有効な方法といえます。
採用コストについては、こちらの記事もご参照ください。
採用コスト削減の7つの方法!コスト増大の原因や削減ポイントを徹底解説
双方向のコミュニケーションが可能
SNS採用の強みは、候補者と双方向のやり取りができる点にあります。
従来の採用活動では、応募者が企業に質問できる場面は限られていました。
しかし、SNSであればコメントやDMを通じて気軽に質問や相談が可能。
例えば、Instagramのストーリーズで質問を受け付けたり、Xでやり取りしたりと、リアルタイムで交流できる環境があります。
こうした対話を通じて、企業側は信頼感を与えられ、候補者も応募前に理解を深めやすくなります。
結果として、企業への関心が高まり、応募につながる可能性が拡大。
SNS採用のデメリット
SNS採用は多くの利点がある一方で、注意すべき課題も存在します。
運用に時間や人手が必要になるほか、炎上リスクや成果までの期間なども考慮しなければなりません。
ここでは、SNS採用に取り組む際に押さえておきたいデメリットを紹介。
炎上リスクがある
SNS採用で特に注意すべきなのが炎上リスクです。
不適切な投稿や不十分な対応が拡散すると、企業の信頼を大きく損なう可能性があります。
過去には公式アカウントによる発言が批判を集め、ネットニュース等で取り上げられたことで応募者が減少した事例も存在。
また、社員や内定者の不用意な発信が火種となるケースも少なくありません。
炎上は一度起これば短期間で広がり、ブランドイメージに深刻な影響を与えます。
そのため、事前に運用ルールやガイドラインを定め、投稿前のチェック体制を整えることが重要。
リスク管理を徹底し、安全なSNS採用の運用を心がけましょう。
運用に工数がかかる
SNS採用は費用を抑えやすい反面、継続して運用する手間がかかる点に注意が必要です。
成果を得るには、定期的な投稿や情報発信を積み重ね、アカウントを育てていくことが大切。
Instagramではアルゴリズムの影響でフォロワー外へ情報が届きやすくなっていますが、応募や採用に直結するまでには時間がかかります。
写真や動画を継続発信することで徐々に認知度が高まり、関心を持つ人材が集まりやすくなります。
つまり、SNS採用は短期的な成果を求めずに、中長期的な取り組みとして位置づけることが重要。
効果が出るまでに時間がかかる
SNS採用は短期間で成果が出にくく、効果が表れるまでに時間がかかる点が特徴。
アカウントを成長させるには、継続的にコンテンツの投稿を行い、フォロワーを増やしながら認知度を高める必要があります。
例えば、Instagramで定期的に写真や動画を発信しても、すぐに応募が見込めるわけではありません。
しかし、時間をかけて情報を発信し続けることで、企業への理解が深まり、結果的に求める人材からの応募につながりやすくなります。
また、即効性を補いたい場合は、有料広告を組み合わせることでスピードを高めることも可能。
採用におすすめのSNS
SNS採用を始める際は、各媒体の特徴を理解し、自社の定めるターゲットに合うものを選びましょう。
ここでは、採用活動に活用される代表的なSNSと、その特性を解説します。
SNS採用については、こちらの記事もご参照ください。
SNS採用代行のおすすめ9選を徹底比較!費用相場・評判・選び方を紹介
LinkedIn(リンクトイン)は、中途採用やハイクラス人材の採用に強みを持つビジネス特化型のSNS。
世界では12億人以上、日本でも400万人を超えるビジネスパーソンが利用しており、専門職やマネジメント層へのアプローチに向いています。
海外人材ともつながりやすいため、グローバルに活躍できる人材を求める企業にも役立つツール。
また、利用者は実名登録が基本で、職歴やスキルが公開されているため信頼性が高いのも特徴です。
求人情報の掲載だけでなく、タイムラインでの発信やダイレクトメッセージを通じたスカウトも可能で、企業の採用活動を幅広く支えます。
| 採用活動での強み | ハイクラス人材や専門職へ直接アプローチできる |
| 特徴 | ・ビジネス特化 ・実名登録 ・職歴やスキルが明確 |
| 利用者属性 | ・中途人材 ・マネジメント層 ・海外、グローバル人材 |
| 具体的活用方法 | ・求人掲載 ・企業投稿での発信 ・DMによるスカウト |
LinkedInについては、こちらの記事もご参照ください。
【採用担当者向け】LinkedIn(リンクトイン)の採用活動での使い方は?
Facebookは、社会人の利用が多く、中途採用に役立ちやすいSNS。
とくに、30代から50代のユーザーが中心で、実名登録制のため情報の信頼性が高い点が魅力です。
企業はオフィスの雰囲気、働き方などを投稿することで、自社の文化を直感的に伝えられます。
求人情報の発信だけでなく、スカウトやコミュニティを通じた交流も可能。
また、Instagramと連携して運用すれば、幅広い世代にアプローチできるのも強みです。
採用活動において、認知度の向上やミスマッチの防止に効果を発揮するプラットフォームといえます。
| 採用活動での強み | 実名制による信頼感、中途採用との相性が良い |
| 特徴 | ・社会人利用が多い ・長文投稿で丁寧な発信ができる |
| 利用者属性 | 主に30〜50代のビジネスパーソン |
| 具体的活用方法 | ・社員紹介 ・企業文化の発信 ・求人掲載 ・スカウト |
X
X(旧Twitter)は、情報をすぐに届けられるリアルタイム性が大きな特徴。
若い世代の利用者が多く、就活生や転職希望者にアプローチしやすいSNSとして活用されています。
拡散力が高いため、採用イベントやインターンの告知を短期間で広められる点も。
さらに、業界の最新情報や社員の日常を発信することで、企業の雰囲気を自然に伝えられます。
ハッシュタグ(#)、リポストを活用すれば、潜在層にも情報が届きやすく、認知拡大と応募促進の両方に効果が期待できるでしょう。
| 採用活動での強み | 高い拡散力で短期間に認知を広げやすい |
| 特徴 | ・リアルタイム発信に強い ・情報収集にも使われる |
| 利用者属性 | ・主に10〜30代 ・就活生や若手転職層が多い |
| 具体的活用方法 | ・採用イベント告知 ・インターン情報 ・業界ニュース発信 ・社員の日常紹介 |
Youtube
YouTubeは、動画を通じて企業の魅力をダイレクトに伝えられる点が大きな特徴。
写真や文章では伝わりにくい職場の雰囲気や社員の表情も、映像なら直感的に理解してもらえます。
とくに就活生や若手層は動画での情報収集に慣れているため、採用広報との相性が良い媒体。
会社紹介や社員インタビュー、1日の仕事密着動画などを公開すれば、求職者に働くイメージを具体的に持ってもらいやすくなります。
また、長尺動画で詳細を伝えつつ、ショート動画で気軽に接点をつくると効果的。
採用活動において、認知拡大から応募意欲の醸成まで幅広く活用できるプラットフォームといえます。
| 採用活動での強み | 映像で雰囲気や働く姿を直感的に伝えられる |
| 特徴 | 長尺動画とショート動画を使い分け可能 |
| 利用者属性 | ・就活生 ・若手社会人 ・動画視聴に慣れた層 |
| 具体的活用方法 | ・会社紹介動画 ・社員インタビュー ・仕事1日密着 ・社内イベント紹介 ・ショート動画での発信 |
Instagramは、写真や動画を中心に発信できるため、若い世代への採用活動に効果的なSNS。
とくに新卒採用との相性が良く、学生にとって企業を身近に感じてもらいやすいのが特徴です。
社員の日常やオフィスの雰囲気をストーリーズや投稿で紹介することで、文字情報だけでは伝わりにくい社風をより直感的に届けられます。
親近感を持ってもらうことで、応募へのハードルを下げられる点も魅力。
また、ハッシュタグ(#)を活用した発信や、リールによる短い動画コンテンツも有効で、幅広い求職者に企業の存在を知ってもらうきっかけをつくれます。
視覚的に訴求できるInstagramは、母集団形成に役立つ重要なツールといえます。
| 採用活動での強み | ビジュアルで親近感を与え、新卒層に届きやすい |
| 特徴 | ・写真、動画中心 ・ストーリーズやリールで手軽に発信可能 |
| 利用者属性 | 学生や20代前半の若手層が中心 |
| 具体的活用方法 | ・社員の日常投稿 ・オフィス紹介 ・ハッシュタグ活用 ・ストーリーズやリールでの発信 |
TikTok
TikTokは、Z世代を中心に人気が高く、短尺動画で企業を身近に感じてもらえるSNS。
とくに新卒採用との相性が良く、学生に自然な形で企業を知ってもらえる点が大きな魅力です。
投稿内容は、職場紹介や社員の一日を映した動画に加え、流行の音楽やユーモアを取り入れることで、多くのユーザーに親しみやすく伝わります。
短い動画は気軽に視聴されやすいため、企業文化を直感的に理解してもらうのにも効果的。
応募を促すきっかけづくりだけでなく、ブランディング強化にもつながるため、若手層をターゲットとする企業には欠かせないプラットフォームといえます。
| 採用活動での強み | Z世代へのリーチに強く、新卒採用で効果的 |
| 特徴 | ・短尺動画中心 ・トレンドやユーモアを取り入れやすい |
| 利用者属性 | 主に10〜20代前半の学生や若手社会人 |
| 具体的活用方法 | ・職場紹介動画 ・社員の一日紹介 ・流行の音楽やハッシュタグを使った発信 |
SNS採用を成功させる戦略
SNS採用を効果的に進めるには、明確な戦略策定が欠かせません。
採用の目的や対象を整理したうえで、適切な媒体選びやコンテンツ設計を行う必要があります。
ここでは、SNS採用を成功に導くための基本的な戦略を紹介。
採用コンセプトの明確化
SNS採用をうまく進めるためには、最初に採用コンセプトをはっきりさせることが大切。
誰に向けて、どんな魅力を届けたいのかを決めることで、情報発信の軸がぶれにくくなります。
具体的な対策
- 理想の人材像を言語化する
例:「主体性を持つ新卒学生」「アクセス解析の知見が豊富なWebディレクター」など。 - 自社の強みを明確にする
他社にはない文化や働き方を打ち出すことで差別化につながる。 - 採用課題に合わせた発信を意識する
例えば、内定辞退の防止や知名度向上など、目的に沿った投稿が重要。
目的が不明確なまま情報発信を続けると、意図しない層に届き、結果的にミスマッチを招く可能性も。
だからこそ、自社の採用課題を踏まえたコンセプトづくりが重要です。
ペルソナに合わせた媒体選定
SNS採用をうまく進めるには、採用したい人材像に合わせて媒体を選ぶことが大切。
SNSごとに利用している層や特徴が異なるため、想定するペルソナに沿って使い分けることで、応募までの採用効果が高まります。
| 媒体 | 主なターゲット | 特徴 |
|---|---|---|
| 新卒学生・20代前半 | 写真やリールで職場の雰囲気を直感的に伝えられる | |
| TikTok | 学生・Z世代 | 流行やユーモアを取り入れ親近感を持ってもらいやすい |
| 中途・ハイクラス人材 | 職歴やスキルが可視化され、専門性の高い層に届きやすい | |
| 30〜50代の社会人 | 実名登録で信頼性が高く、中途採用との相性が良い |
新卒採用では「Instagram」や「TikTok」が向いており、写真や短い動画で社内の雰囲気をわかりやすく学生に伝えられます。
一方で、中途採用では「LinkedIn」や「Facebook」が有効で、職歴やスキルに基づいた判断で企業から直接、人材に対してアプローチができます。
業界や職種によっても最適な媒体は変わるため、自社の採用目的と照らし合わせて選ぶことが重要。
コンテンツ戦略と発信例
SNS採用を成功させるには、ターゲットに合ったコンテンツを計画的に発信することが重要。
写真や動画、文章を組み合わせることで、職場の雰囲気や働く姿をより具体的に伝えられます。
とくに動画は臨場感があり、応募意欲を高める効果があります。
発信の工夫次第で、候補者に強い印象を残せる点がSNS採用の大きな魅力。
発信例
- 社員インタビュー(キャリアや働き方を紹介)
- 1日の仕事風景(密着形式でリアルな様子を公開)
- 社内イベントやプロジェクトのレポート
- オフィス紹介や日常の雰囲気を伝える写真投稿
KPI設定と効果検証
SNS採用を効果的に進めるためには、KPIを設定して定期的に確認することが大切。
フォロワー数だけに注目するのではなく、実際の応募数やエントリー数、面談につながった件数といった指標を見る必要があります。
「1カ月で説明会エントリー20件」など、具体的な数値を目標にすると改善点が見えるはずです。
定期的に数値を確認し、投稿内容や媒体の活用方法を見直すことで、より成果向上に期待。
SNS採用の成功のコツ
SNS採用を効果的に進めるには、戦略を立てるだけでなく、日々の運用や工夫が成果を左右します。
ここでは、SNS採用を成功させるためのコツを3つ紹介。
社員を巻き込む
SNS採用を効果的に進めるには、社員の協力が必要。
人事担当者だけの発信では情報が限られ、実際の働く姿や雰囲気が伝わりません。
現場で働く社員が登場することで、企業文化や日常の雰囲気を自然に伝えられます。
例えば、社員リレー投稿やインタビュー動画を用意すれば、多角的な視点から会社の魅力を発信可能。
そのためには、社内で協力体制を整え、発信を業務の一部として位置づける工夫も重要です。
社員の声を積極的に取り入れることで、応募者に親近感を与えましょう。
継続運用の仕組みづくり
SNS採用を効果的に進めるには、無理なく続けられる仕組みを整えることが大切。
思いつきの発信では成果につながりにくいため、計画的な運用が求められます。
継続運用のポイント
- 投稿スケジュールを決める
週単位や月単位で計画を立てると、更新が途切れにくくなります。 - 担当体制を整える
専任チームを置く、もしくは一部を外部に委託して負担を分散させます。 - 習慣化する仕組みをつくる
定例業務に組み込むことで、自然に発信を継続できます。
上記のポイントを押さえることで、安定した発信を継続でき、SNS採用の成果につながります。
炎上リスクの管理
SNS採用を安心して進めるためには、炎上リスクを管理する仕組みが必要。
不適切な投稿や対応の遅れは、企業の信頼低下につながる恐れがあります。
そのため、投稿前に内容を確認するチェック体制を整えておきましょう。
さらに、ネガティブコメントにどう対応するかをあらかじめルール化しておけば、現場の混乱を防止。
社内ガイドラインを明文化し、担当者へ周知徹底することも欠かせません。
日頃から体制を整えておくことで、リスクを未然に防ぎ、安心してSNS採用を運用できます。
よくある質問【Q&A】
SNS採用を検討する際に、費用や効果、どのような企業に向いているかなど、気になる点も多く存在。
そこで、採用担当者から寄せられる質問を「Q&A形式」でまとめました。
効果はどれくらい出る?
SNS採用は短期で大きな成果を得るより、中長期で効果が表れやすい方法です。
半年から1年ほど継続して発信することでフォロワーやエンゲージメントが増え、応募につながります。
短期的な効果を狙う場合は広告を活用するのが有効的。
無料でできる?
SNS採用は、アカウント開設や投稿自体は無料で始められるものがほとんどです。
ただし、効果をより高めたい場合は、有料広告を活用するのも一つの方法。
さらに、社内だけでの運用が難しいときには、外部の代行サービスを利用する選択肢もあり、その際は代行費が必要になります。
どんな企業に向いている?
SNS採用は、若手や新卒を迎えたい企業に向いている採用方法です。
IT企業やベンチャー、サービス業のように企業文化を伝えることが重要な業界で効果を発揮。
また、BtoB企業でも採用広報やブランド発信の手段として非常に有効的です。
SNS採用で「攻め」の採用広報へ
この記事では、SNS採用の特徴や従来手法との違い、さらにメリット・デメリット、成功させるためのコツまでを詳しく解説しました。
SNSはコストを抑えながら幅広い層にアプローチでき、動画や画像を活用して企業文化をリアルに伝えられる点が大きな魅力。
一方で、炎上リスクや運用負担といった課題もあるため、ガイドライン整備や継続運用の仕組みづくりが欠かせません。
採用ターゲットや目的を明確にし、本記事で紹介した媒体ごとの特徴や運用戦略を参考に、自社に合った活用方法を検討してみましょう。
「攻め」の採用広報としてSNSを取り入れることは、優秀な人材をつなぎとめる強力な手段となるはずです。